
8からの買い替えです。9になって少し変わったと感じることは、音源がひとフレット増えたこと、途中でフリーズをしなくなったこと。これが素人目に最初に感じた印象です。PCが2コアなのでエンコードに無茶苦茶時間がかかりました。友人のi7・860の時なら4分の一で済みましたので、今4コアのPCに買い替えるべきか動画の使用頻度を模索しているところです。1週間に一度くらい20分動画のエンコードをするのであれば自分なら即買い替えですが自分は一カ月に一度15分動画をエンコードするくらいなので少し迷っています。ということで自分が今率直に感じていることです。あとトランジションが少ないことズームアップができないこと、文字の入れ込みメニューが少ないこと、動画のフレームがもうひとつフレームがほしいことなど要望したい気がします。しかし使いやすさでいえば8から使用しているのでなれています。
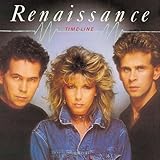
83年発表の10作目。ニュー・ウェイヴ仕様の第二弾だが、本作を持ってアニー・ハズラムをフロントとしたルネッサンスは一旦幕を閉じて長い活動停止に入る。(95年にマイケル・ダンフォードが新たにステファニー・アドリントンを迎えてグループを再編。その後もアニーを再び迎えて断続的に活動を行なっている。)
1.はワーナー時代に戻ったかのようなシンフォニック色とポップ色が融合した彼ららしい仕上がり。キーボードが音色、フレーズ共にかなり70年代を意識しているのが伺われる。2.は一変して80年代風の軽めのドラムス/ギターが聴かれるが、メロディ・ラインや展開などは70年代を彷佛させトータルとしての仕上がりは上々。3.は80年代の彼らの代表曲の一つであろう。メロディ展開の素晴しさ、そしてそのメロディそのものの美しさはまさに屈指の出来栄。4.はどことなくプロンディを彷佛とさせるトロピカルな一曲。こういう路線への展開もおもしろかったでは?と思う。サックスが入った6.も同路線でこりゃたまらん!!的な仕上がり。9.も同様に歌い方を含めてプロンディ風だが、本格的なサックスのアンサンブルがなかなかの聞き物。
80年代のルネッサンスは時代の流れと自らの音楽性に折り合いが付けられずに苦悶していた印象があるが、むしろ変化出来なかったことで本作のような名作が残された。ある種の不器用さは職人業と言い換えることも出来よう。
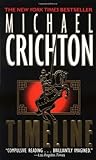
最近のクライトンは、かなりワンパターンになってきた。なぜか。内容が変わっても、スタイルが同じだから。ほとんど、駄菓子屋ののり。ただ、そこが圧倒的に良い。最初のページから、終わりのページまで、ぐっと引き寄せられ、そして彼の設定した世界の中に、無理矢理監禁状態となる。既に知られている最新の科学技術を、彼一流のやり方で、おおげさにセンセーショナルにプレゼンテーションする。最新作、"Prey"は、若干、求心力が劣っていたが、この"Timeline"は、上記のプレゼンがうまくいっている。職人的にうまい構成力に、後は徹夜で酔うだけ。私は良く英文で物を書かなくてはならない事があるのですが、彼の文体は非常に役に立ち助かっています。上手い文章を書こうとしたらまずは彼のストーリーテリングの手法をまねするに限ると思っています。

仕事柄、業務用のシャトルも使いますが、この値段にしては反応もよく、プリセットも自由にできるので良いです。
EDIUS、FinalCutProでの使用感です。
大きさもこのぐらいがちょうどよいと感じます。
ドライバーもHPで更新されていますので、安心だと思います。

本書は「量子コンピュータとは何か」(2004)の文庫化です。文庫化に際し、量子コンピューターの研究者・竹内繁樹による解説が加わり、原著(2003)以降の進展のおよび参考文献の紹介がなされています。
本書はサイエンスライター(「聖なる対称性―不確定性から自己組織化する系へ」「もうひとつの『世界でもっとも美しい10の科学実験』」)が如何に量子コンピューターを理解したのか、その思考の跡が行間から読み取れるという点がユニークだと思います。(具体例に噛み砕いて説明する処から、それが読み取れます)
"量子コンピューター"を理解するために、まず"古典的コンピューター"を著者の経験談を交えながら平易に解説しています。そこで(古典的)コンピューターの本質は装置の"素材"ではなく"構造"(素材の組み合わせ方)にあることを指摘しています。(玩具「ティンカートイ」で作った"三目並べ"マシーン) そして突き詰めれば、コンピューターの中身は全て1と0の繋がり、微小なスイッチのオン・オフでしかないわけです。ここで読者はコンピューターのデータの最小単位・ビット(bit, binary digit(2進数字)の略)を自然に理解することができます。
このbitの概念が「量子コンピューター」では"1と0の状態の量子力学的重ね合わせ状態"(qubit, quantum bitの略)に置き換わっているわけです。そんなモノを考えることの御利益(超並列計算)および実現方法(及び"実現困難さ")が比較的平易に説明されています。「P≠NP? or P=NP?」にまで話題を拡げている処は良いですね。なお暗号の話題は「暗号解読(上)」「暗号解読(下)」と併せて読むと面白いと思います(特に下巻)。
注が充実しており、著者がどういう文献にあたって量子コンピューターについて勉強したのか辿れます。そういう意味でも参考になる本です。量子力学の概念に馴染みのある読者であれば楽しく読み通すことが出来ることでしょう。(文系の人には少し難しい箇所があるかもしれません)
| 
