
日本語がこんなに表現力豊かな言葉だったというのを初めて認識。
優しくて残酷・美しくてグロテスクなどの相反するイメージの奔流に圧倒されてしまい、読み終えてしばらくは頭がクラクラして他のことを何も考えられませんでした。
こんなモノを書く人の頭の中を割ってのぞいてみたい・・というのは思い付く最大級の褒め言葉デス。
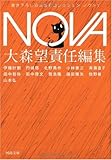
11編中、
「お、なかなかおもしろいなあ。この作家の他の作品も読みたいなあ」
と思ったのが5編、
「ん〜、波長が合わないなあ。読むのに忍耐を要したなあ」
と思ったのが4編(うち2編は長い!)、
でした。
第2巻も出るようですが、少し待って古本で安く買ったほうが無難かな。

「SFマガジン」で短編をいくつか発表して、高く評価されながらも、ここ10年は沈黙していた幻のSF作家、飛浩隆の新刊にして初の長編(私もこの作品で知ったんだけど)。 舞台はコンピューター上に存在する、今は放棄された仮想リゾート。サイバースペースものとしては、この舞台自体はそれほど斬新なものではないが、現実の人間=ゲストが千年間訪れない世界で、ゲストを歓待するために存在するAIたちを描くという設定が秀逸。AIたちは、自分がAIであることも、この世界が何らかの理由で放棄されていることも認識している。それゆえに、この穏やかな、停止した世界は、美しいと同時にどこかもの悲しい。その平和な世界に「蜘蛛」と呼ばれる存在が、突然攻め入ってきて、AIたちと「蜘蛛」の戦いがストーリーの中心となる。 この物語は残酷だ。AIは次々と「蜘蛛」に殺されていく。とびきり残酷なやり方で。最大限の恐怖と苦痛を与えられて。そしてAIたちが追い詰められていくうちに、ゲストの歪んだ欲望をぶつけられるこの世界そのものが、実はひどく残酷なものであることが浮かび上がってくるのだ。 しかしまた同時にこの物語は美しい。世界観を支える様々なアイデアは、非常に美しいイメージを喚起させる。残酷な世界の中で、語られるAIたちの心情も繊細だ。相当に救いのない話であるのに、その読後感はさわやかである。
作者はあとがきで「清新であること、残酷であること、美しくあることを心がけた」と語っているが、まさしくその通りの作品。

ロボット・AI研究者による研究発表は、思っていた以上にSFの世界が現実のものとなっており、驚きの連続であった。
冗談を交えながら一般の人々にも分かりやすい形でプレゼンされており、すんなりと理解できる内容だった。
SF作家による書き下ろしの短編小説は、これだけを読んでも十分面白い。
これが科学者の問いかけに対するアンサー・ノベルとなっているだけでなく、さらに科学者を刺激する内容にもなっている、
という見かたをすると、また違った面白さを感じることができる。
科学者により創造されたものが、作家の想像力を刺激し、その想像がさらに科学者を刺激する。
科学者と作家という異分野の人々が織りなす素晴らしき世界を味わえる稀有な一冊である。

『グラン・ヴァカンス』に続く中短編集。三部作第二部。
前作では物語設定上、SF的要素を極力廃した語り口であったが
本作ではその呪縛の鎖を、力技で解き放つかのように
華麗な筆致で、鮮やかに「仮想世界」を描ききっている。
視覚的なきらびやかさだけではなく、
その手触りのリアリティも、まこと秀逸である。
しかし詩的に、そしてグロテスクなだけではなく、
ラストを飾る中篇「蜘蛛(ちちゅう)の王」の
疾走感溢るる跳躍の描写は、こんなこともできるのかと
舌を巻く出来である。
| 