
本CDは岡田暁生氏の『CD&DVD51で語る西洋音楽史』(新書館)において2番目に引用されたもの。単旋律の単調さは退屈といえば退屈ではあるが、曲想の厳粛さは教会のひんやりとした静謐さを感得させ、何かこう粛然とさせられるものがある。思えば、同書で最初に引用された『地中海のクリスマス』に収録された作品群と本CDの作品群との「落差」こそが、非西洋キリスト教世界から西洋キリスト教世界への「純化」の歴史的過程を如実に物語るのであろう。
「鳴り物や手拍子やしわがれた声といったノイズで溢れた「土着の」音楽に熱狂していた異教徒たちを、静けさに満ちたキリスト教の神の国へと帰依させる。そんな使命を、聖歌は担っていたのだ」(同書16頁)。
「中世の芸術に共通するのは、生きた感情と身体を欠く不思議な抽象性である。恐らくそれらは生身の人間が楽しみ味わうものではなく、魂が身体から遊離した後の彼岸世界の予感であり、「この世ならぬもの」の顕現の告知だったのだろう」(同)。
「当時の人々にとっての本来の音楽とは、この世界を調律している秩序のことだった」(同書17頁)。
なお、念のため同書16頁に示された「図1」だが、本文との対応関係が全く違っている。誤挿入であろう。

実話を元に作成された作品です、主人公(ベルナデット)のような、
心清らかな方が実在したのかと思うと、ただただ、感動致しました。

前作をやった人はやったほうがいいです
正史扱いかはわかりませんが真エンド的な展開があります
聖なるかなのキャラも何人かちょい役で出ます
正史扱いならぜひ次の作品にもみんなで出て欲しいものです
えちシーンが各キャラもう一回くらいずつ欲しかったので4つ

このアルバムの巧みさは、まずもってその構成にある。まずは、寺院の門前で喧しかったであろう「教会の入り口で演じられている楽師や物乞いの芸」の曲たちが配置され、次に「教会への入堂」のための曲たちが、そして最後に「ノートル・ダム・ミサ」が配置されている。これにより、聴者は教会の内外に流れていたサウンドを追体験し、ひいてはいわば中世ヨーロッパの街角の喧騒(的なもの)を感得することが可能となっている。
猥雑さと崇高さと、俗と聖と、中世ヨーロッパ文化の諸相を「感じる」ための正に必聴の一枚ではなかろうか。
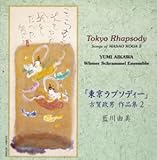
いわゆる「演歌」はきらいな私だが、このCDを聴くと、日本人の琴線にふれるメロディーと歌詞に思わず浸ってしまいます。おまけに伴奏陣が19世紀ウィーンの庶民音楽であるシュランメルを現代に受け継ぐ外国人と聞いて、単なる日本趣味を越えた古賀音楽の懐の深さに驚くばかりです。藍川さんの著作「演歌のススメ」(文春新書)を併読されんことを。
| 

