
まほちゃんの家
しまおまほさんとは丁度同じ世代です。それを考えると、「お風呂も水道もなかった」エキセントリックな家で育ったまほさん、ご両親のポリシーを感じます。おばさんのマヤさんとの交流、人の死について思うこと、失恋、本当に繊細な人だなと思うと同時に、冷静な観察眼はさすが!と思いました。高校生のときにお昼の45分をどうやって過ごすか悩んでいたあたり、ああ、普通の高校生(そしてクラスに一人、そういう人がいるかもしれない)の夢破れた雰囲気がよく出ていました。
これからもエッセイを読みたいです。漫画で読むより人柄がしっくりとよくわかりました。

死の棘 (新潮文庫)
本というものは読んでも読んでもこの世に数多あり読み尽くすことなどとてもできない。また2度3度
読み返すこともあるわけだから人間生きているうちにいったいどのくらいの本に出会えるのだろうか。
しかしその読書という長い旅のうちに何度かは飛び切りの出会いがある。 まさしくそれがこの作品であった。
自分にとってほんとうに偉大な作家・作品との出会いは、今までウィリアム・フォークナーであったり、
ヘンリー・ジェイムズであったけれどこの作品はそれらの体験に勝るとも劣らない衝撃的な出会いであった。
この見事な日本語で書かれた美しい物語は読み終えたあともいつまでもこころの中から消えない。
寧ろ時間が経つほど波紋のようにこころに染み入っていく。
これはほんとうの物語。ほんとうの愛の物語である。

ナニカアル
林芙美子は毀誉褒貶激しい作家だということは知っていた。私が読んだのは、「風琴と魚の町」「放浪記」「浮雲」だが、詩情のある文章を書く人だと思った。また「浮雲」の女性は殺しても死なないタイプ、というか、生きるエネルギーが有り余っているといった感じであったが、この「ナニカアル」に描かれた林芙美子にも同じ匂いがあった。
作者は林芙美子の手記に擬してこの物語を書いているのだが、いかにも林芙美子が書きそうな文章(詩情あふれる文章)であったのがおもしろかった。戦時中の異常な空気が迫真に迫って描けていて、ボルネオの農園の人々の悲哀、言いたいことも思うとおり書けない現実、そんなものが心に強く残った。また、芙美子の当番兵野口と松本のなんともいえない気味悪さが良く描けている。デング熱にかかった野口が「放浪記」を読んでいるところが、一人の人間の行動としていかにも納得でき、そしておもしろく、思わず笑ってしまった。
芙美子の情事の相手となった架空の人物、謙太郎がいかにも弱そうなインテリで、ここにも「浮雲」の男性の影を思わず重ねてしまった。
私にとって、この小説のおもしろさは、そういった現実世界の林芙美子とこの小説の中の林芙美子を重ね合わせるおもしろさにあったように思う。
世の中には道徳があって、皆それに交通整理され整然と生きているが、素のままに生きればこの主人公の芙美子のようなものかもしれない。それはまた、いつ死が訪れるかもしれない戦争の中にあったからこそではないか、とも感じた。
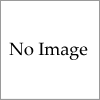
死の棘 [VHS]
小栗監督の作品をゆっくり観てきた。本作だけが未見だったが ようやく今回観る機会を得た。
「死の棘」という言葉は新約聖書コリント人の手紙1の15章から採られている。「死の棘は罪なり、罪の力は律法なり」という一文だ。
本作は夫の浮気という「死の棘」が刺さってしまった家庭の話である。
夫の浮気は別に珍しくもなんともない話だ。陳腐と言って良い。但し 本作が展開する「棘」とは そんなありきたりな話では済まなくなっていく。観ているうちに 狂気に走っているのは妻なのか夫なのかもはっきりしなくなっていくからだ。
しかも 監督は 幾分非現実的なセットを用意して本作を撮っている。観ていると 映画というより演劇のように感じてくる。おまけに季節感が狂ってくる。夏の場面の次には 正月の場面であり まもなくススキが写りだされる。時間の推移ということなのだろうが 観ているこちらとしては 空間的にも時間的にも 混乱させられてくる。観ている場面の季節すら良く分からなくからだ。
狂っているのが 妻や夫だけではなく 観ているこちらまで狂っているような気がしてくるから 不思議だ。
本作の最後に 「救い」は用意されていないと僕は観る。最後の場面に「治癒」が見えるとも思えない。僕らは宙釣りにされたまま.....幾度か首を釣ろうとして失敗していた夫と妻とは違って......本作を観終えることになる。これも得難い体験だ。








