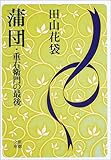志は挫け恋にも破れた主人公の孤独の心情、その寂しさをあの手この手で遣り過ごそうとする悪足掻き(友人への嫉妬、生活に安穏とする同僚への軽蔑、日々の労働とは無関係の素人研究への熱中、上級資格の検定試験を受けて何とか成り上がろうとする試み、幼いがゆえに純粋な者たちと接する中に見出す慰め、商売女との仮初の交わり、遠いところへの憧憬、世捨人然とした生活、諦念と沈黙・・・)、それが今までの自分の姿と重ねられる。
"あゝわれ終に堪えんや、あゝわれ遂に田舎の一教師に埋れんとするか。明日! 明日は万事定るべし。"
自己の内面に一度でも沈潜してしまった者は、その深淵に比して自らを捕り囲む実生活の尺度が余りに卑小であることに、軽蔑と戦慄を覚える。唾棄すべき俗世の中で何者かとして固定され埋れてしまうことへの恐怖。つまらぬ日常は、それこそ毎日、補給され続ける。
内的な理念によって自らを吊り支えることも能わず、他者と情愛を遣り取りする合せ鏡の間に自己の居場所を見つけることも叶わず、かといって世俗の汚泥に頭まで浸かりせいぜい実利計算にばかり長けた小賢しい愚鈍の俗物に堕することも潔しとしない。自殺もできぬ、発狂もできぬ、宗教にも走れぬ。せいぜいが、束の間、生理的快楽に孤独を紛らわせるくらいしかできない。
内的な信念への重苦しい誠実さを抱え続けること、実生活の尺度に合わせて「小さく生きる」こと――ルカーチならば、節制 Haltung と呼ぶだろうか――、如何にしてその折り合いをつけていけるものだろうか。執着か妥協か、何が本当なのか分からない。
嘗ての教え子である女生徒の中に清三の影が残っていることが、救いだ。

自然主義文学の旗手として名高い、田山花袋の温泉紀行。
その足は本州から九州に至る全国に伸び、まだ見ぬ登別の温泉にも想いを馳せます。
小説執筆の傍ら、地理の仕事にも携わってきたという花袋だけに、その筆はなかなかに詳細です。
しかし一読して思うのは、その破天荒とも言うべき文体と構成です。
主題と内容が一致していなかったり(藪塚温泉の項)、
また視線の動かし方が唐突で、花袋の想いが関東の温泉から突如九州まで飛んで行ってしまったりする。
読み手にも地理的感覚が要求され、それがない読者は当惑すること間違いなしです。
文体もまた、漢文的表現と散文がごちゃ混ぜでしかも定型的な表現が何度も繰り返され、
読み進めるうちに鼻について仕方がないという感を抱くことも。
「また山巒に嵐気の幽邃かい」
と突っ込みを入れること数え切れません。
一方、雑多なさまはなんでもかんでも「ゴタゴタした」で片付けられてしまい、
しかも最後に「温泉とはそういうものだ」と言い、故に「別府こそ一番だ」と言い切ってしまう。
それまで長々と「嵐気が」「幽邃が」と言っておきながら、何故にその結論かと。
しかしそれでいて憎めない何かがあるのが彼のパワー。
伝統的な山水の風景観と、近代の科学的かつ自由な風景観が、彼の中で共存していたのでしょう。
花袋の文学が漢文的な文体からやがて飾りなき「自然主義」に移行していったことからも、それは窺えます。
そう考えた時、明治以降日本人の美観というものがどう変わって行ったか、花袋を通じて興味深く読み取れるのです。

キャラクター小説とは、ライトノベルのことです。本書の元となった「ザ・スニーカー」の連載時点においてはライトノベルという言葉は生まれていなかったので、大塚が「角川スニーカー文庫のような小説」を総じて命名しました。
題名は小説入門書を装っていますが、内身はちがって大塚の小説論になっています。実際、創作支援書として具体的アドバイスを行っているのは全12講中2・6・8講くらいで後は小説批評といえる代物です。そこでは、今ひとつジャンル名が定まっていなかった現在ライトノベルといわれる小説群のルーツと定義、独自性を洗い出します。これはこれで充分面白いのですが、面白いラノベの書き方を手っとり早く教えて貰いたい読者にとっては不親切です。
なぜ、こんな本になっちゃったかの理由ははっきりしています。雑誌連載時の創作入門書としての中核である「宿題編」が新書版及び文庫版に未掲載だからです。「宿題編」とは毎号の最後で読者に対し課題を出し、次号においてその募集された課題をもとにプロット及び設定を組み立てていき、最終的には小説を一本作ってしまおう、という試みです。つまりこの本は本来「物語の体操」と同じ路線の書き込み型の創作入門書になるはずだったのです。連載時のあおりでは、連載を読んでるだけでキャラクター小説をまるまる一本作る疑似体験ができるよ♪ってな感じでした。それがゴッソリなくなっているのですから書籍化にあたっては書名を変えた方が誤解を受けなかったかもしれません。
大塚の小説批評としての最終的な主張は以下の通りです。明治三十年代の若者達が西欧化という新しい現実を前に言文一致体からなる新しい小説を生み出したように、現在も新しい小説が生れていく変化の渦中にあるのではないか、その可能性の一つとしてライトノベルに期待したい。という希望に満ち満ちた結論です、でした。(今は投げやりな諦めムードに向かってますが)

日本の文学史的名作とされるけど、改めて読んでみると主人公と作者の混在も相まってか、うーん、何だかなーという気持ちになる。もちろん私小説を開拓した作品ではあるが、主人公さん、これってあり? でも、そう思わせることが意図だとしたら、人間とはこうも一貫しないものという意味で、まんまと術中にはまったということか。脈絡無い言い方をすれば、松本清張の或る「小倉日記」伝をその後読むと、好対照な感じがする。
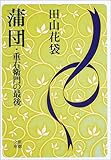
「蒲団」が発表されたころ『三四郎』も出ている。三四郎はのぼりの東海道線で一緒になった
謎の女性と宿を共にし、一つのふとんを二つに分けて寝る描写がありますが、これは明らかに
三四郎の晩生(おくて)ぶりをあざ笑うためのものであって、ということは、当時の日本人は
性愛について、今から思うほど閉ざされたものではなかったのである。その状況が、「蒲団」を読むと実によくわかる。それなりに主人公は煩悶しているが、そのさまは滑稽とは思えない。むしろ、主人公の口ぶりのように当然であるかのようだ。恋と愛とは異なり、恋愛と結婚は一つの延長線で結ばれているわけではない。当たり前だが、この21世紀になっても、そこのところがよく理解されていないように思います。ということで、明治の男だって悩んでいたのだ。貴兄の悩みは無理からぬことだ。
|