
冬の旅 (新潮文庫)主人公が少年であるので、立原にはめずらしく女の情念がドロドロしてこない。主人公は大人びていてちょっとかわいげがないともいえるが、厳しい自らの生をまっすぐ見据えて立つ姿勢は見事。身を切るように冷たい中で、清澄な輝きを見せる冬の早朝のような読後感だった。とくに中・高校生から大学生に薦めたい。 
残りの雪 (新潮文庫)
この作品の文学的印象は別の方がいろいろ書いておられるので、

春の鐘 (上巻) (新潮文庫)美術史家鳴海六平太とその妻、陶工の娘の三人が主人公。妻が夫の永の留守に倦んで不倫に走る。男といる現場を夫に目撃され、それが契機となって妻は更に別の男とも不倫を重ね、転落していく。夫は赴任地奈良で、陶工の娘と深い仲に陥る・・・、取り立ててユニークな筋立てではない。奈良の寺/仏像、韓国の古陶磁器、更に美食に関する作者の蘊蓄が全編にちりばめられる。鳴海と陶工娘は休日のたび、唐招提寺をはじめあまたの名跡に仏像参拝に出かけ、帰りにレストランで高価な食事をとる。よくも暇と費用が続くものだ。また鳴海と陶工の娘は類まれな好色、ほとんど毎日セックスしているかのようで、よくもこんな頻繁にできるものだ等、変な心配をしてしまう。場所やメニューを変えて、類似の場面が数十回(?)出てくる。鳴海は妻を悪い女だと不満に思うが、自分も陶工の娘と同棲する、どっちもどっちと言えなくもないはずなのに、他人にかなり偉そうに口を利いているのが笑える。映画で鳴海を演じた北大路欣也の印象によく合っている。ま、作品の目的は作者の美(古跡、仏像、陶器、食、性)意識を開陳することにあるようで、人間は付け足しと考えるべきか。非現実的部分が多いのを承知で読むこと、を作者は求めたのかもしれない。 
薪能 (角川文庫)この作者の日本や日本文化に対する姿勢というのは、何か必死なものがある。それは自身の出自に依るものだろうと一般には言われている。「日本の滅びのことしか考えていなかった。滅び行くものの他は一行も詠うまい。そんな決心をした人もいた」(情炎)、というような主人公の独白を読むとき、そこまで追い込む作者の執念には圧倒されてしまう。 日本の古典文化への傾倒という点では、「活花の師匠が、如何にして上手に花を活けるか、という技巧に熱中しているなかで、(中略)・・・花器や壺に無造作にひとつかみの花を投げ入れ、あるいは小さな湯呑茶碗に一輪さしの花を添えたりした」(情炎)と言うような箇所に、神髄に固執する作者の心根が感じられる。世阿弥の「花伝書」の語句を冠した作品もある!作者にとっては現代風の装飾過多な風潮というものには苦々しさを感じてならなかったのだろう。 本作品集では主人公達(概ね不倫関係にある男女だが)は自分で自分を追いつめ、孤立して破滅していってしまう。作者は、日本文化に対する確固たる視点を持つ主人公達を、繰り返し追いつめ、破滅させることで、自分の身代わりとして自身の破滅を回避して延命するつもりだったのだろうか。やはり圧倒される執念だ。 
美食の道 (グルメ文庫)
筆者の食への思い入れが
|

|
"Spring Powder" from "春の鐘" played by ocha『久石譲/サントラ・ベスト・コレクション(ドレミ)』から『Spring Powder』 ~ 『春の鐘』より作曲:久石譲編曲:青山しおり春の粉?意味がちょっと分かりかねます。 |
|
【中古】 立原正秋風姿伝 / 鈴木佐代子 【去年の梅】は、竹西寛子さんの作品ではないですか? 2月17日(日)のつぶやき もっとも感情を描かないハード・ボイルド作家 片岡義男『本 ... 立原正秋の著書について、教えて下さい。 立原正秋氏(作家)の作品の中で好きな小説ありましたら、よろしくお願いします、 ... 立原正秋全集 第24巻/立原正秋【クーポンがもらえる!読書家応援キャンペーン実施中!】【RCP】 立原正秋全集 揃 【中古】afb 小泉八雲よろしく、日本人みたいな名前で、(当字含め)本を出版した海外出身の作... 昔のドラマ「冬の雲」 直木賞作家、故立原正秋さん著の『冬の旅』読んだ事がある方、 感想を聞かせてもら... |

フィル・ライノットCozy Powell - Killer 
佐々木敏佐々木 敏30 2011徳商マスターズ 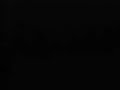
エドウィンEDWIN JEANS 
星座盤自然與生活科技-認識星座盤02 
合格者慶應大学合格者インタビュー。約一万人中10位!上位0.1% 
奏雨マルチーズ 舞と奏 雨の日のバギー 
メタボリック祇園祭 '2012 (034) | メタボリック対策TV 
高山寺京都高雄 世界文化遺産 高山寺 |
[動画|ゲーム|ヤフオク]
[便利|辞書|交通]
[ランキング|天気|メル友]
[占い|住まい|ギャンブル]
Rajnikanth in Oruvan Oruvan Mudhalali - Muthu
感染症〜ワカメハザード〜
立原正秋 ウェブ